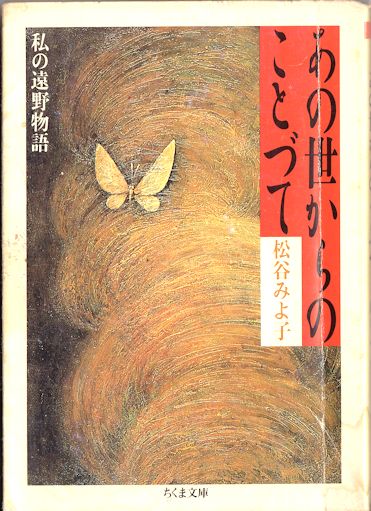
あの世からのことづて-私の遠野物語 松谷みよ子 著 筑摩書房
カバー装画 松谷春男 筑摩文庫版 1988年10月25日第一刷発行 ISBN4-480-02267-8 C0193
この作品は1984年12月15日、筑摩書房より刊行された。
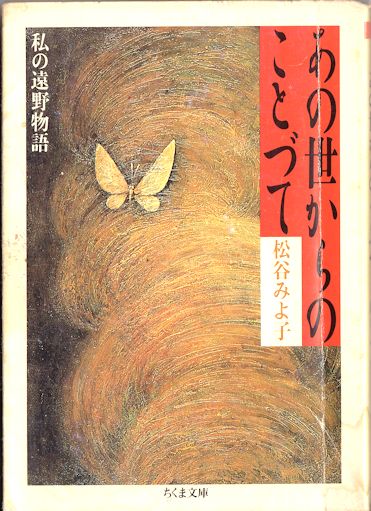
川を渡りかけ、あるいは花野に出……あの世とこの世の境で引き返した人の話、自分の死を告げに来た人の話、火の玉の案内で命拾いした人の話など62篇。現代にふつふつと生まれ続ける民話を追いかけて全国を歩く著者が身近に聞いた世にも不思議な話を収める。解説 吉沢和夫
まえがき
長い間、柳田国男の『遠野物語』に惹かれていた。しかしどこかで、これは遠野だからある話で、どこにもここにもあるものではない。まして初版が刊行された1910年(明治43年)から数えても、長い歳月が経っている。明治以降、人間の生活がどんなに大きく変ったかを考えれば、たとえ遠野の世界があったにせよ、もはや語られることはあるまい。
そんなふうに考えてもいた。
それとは別に私は、これまた長い間、現代の民話という言葉にこだわり続けてきた。人間がそこにあるかぎり、ふつふつと民話は生まれていると信じていたからである。事実、旅の中で、あ、これは現代の民話だと思うことも珍しくなかった。
興味深いことに、一つの話にはいつか必ず連れがみつかった。こういう話にしようと相談したわけでもないのに、同じ型の話が、北と南にあったりする。この普遍性が、点と点ではなくて、もし線になることが証明されれば……いや、面たり得ることが立証できれば・・・・。
この思いは1978年(昭和53年)、私ども日本民話の会が『民話の手帖』という全国誌を発行したことによって一歩を進めることができた。聞書・アンケート・資料等による「現代民話考」を連載することができたからである。成算があってのことではなく、無謀とも思える試みであった。曰く、密造酒、偽汽車、天狗、河童、学校の怪談、ラジオ・テレビ局の笑いと怪談、軍隊。そしてあの世へ行った話、夢、生まれ変り、神かくし等、回を重ねていくうちに私の中に何ともいいようのない不思議な世界が拡がっていった。まさしくこれは、遠野の世界ではないか……。
私は民話を集めようとしたのに、あらかたの人は、あったること、として、自らが出逢った真実を述べている。もしかして、遠い昔、いや、すこし昔の出来事は、いつのまにか民話として席を占める結果となったが、本当は、あったることだったのではなかろうか・・・。
柳田は『遠野物語』の序の中で、
-要するに此書は現在の事実なり。単に此のみを以てするも立派なる存在理由ありと信ず。と述べている。異なるのは、佐々木鏡石という一人の人よりの聞書であり、遠野という一つの土地に限定されていることで、僭越をも顧みずにいうならば、「現代民話考」は日本全国、いや、戦争中は中国や南方の島々をもふくむ広大な地域での、あったること、であり、多くの人々の証言なのであった。
六年目に入った今、この仕事に目をむけてくださる方も多い。しかし一方では、危惧の念を抱く人もいた。夢の知らせやあの世の話に至ると、「松谷さん、オカルトにならないでくれ」という青年もいた。思わずふきだしたが彼は不安気であった。自分はどっぷりとそういう世界に浸っているからなお案じられるという。ならばその話を聞かせてと逆にねだって話して貰ったのが、第一話の、死者からの知らせである。
1 死者からの知らせ/2 吹雪の夜ばなし/3 ヘチマ模様の浴衣の女/4 湯をもらいにくる/5 故郷へ帰る死者/6 寺へいく死者/7 洗濯屋のお婆さん/8 ああ、らくらくした/9 赤ちゃんの棺えらび/10 百日紅(さるすべり)の花の上で/11 あの世の川へ出る/12 イミズガヤリ/13 花 野/14 川と花野と/15 あの世からのことづて/、16 死者からのたのみ/17 悦子ちゃんと人形/18 卒業式に出た魂
18卒業式に出た魂
宮城県の、とだけいっておく。少しく差し障りもあるからとその人はいう。これも死んだ子の話である。
昭和50年の夏休みのことであった。六年生になる男の子が親戚の人と浜へ泳ぎにいって溺れ死んだ。親はその子が中学に入るのを楽しみにしていて、まだ夏だというのに制服からかばんから帽子からみな揃えてあった。そこへ溺死の知らせだったから、その悲しみは見るにたえない程だったという。
担任の先生はその子を五年、六年と受け持っていて、次の年、いよいよ卒業というときに、
「校長先生、これまで生きて勉強してきたんだから、みんなと一緒に卒業証書なゆとくれてやってくれ」
とお願いした。中学にあがられねえんだから、せめて小学校の卒業証書やりてえって。
ところが校長先生はがんこで、死んだ者にはやれねえという。死んだ者だからくれたっていいでねえか。担任の先生は校長に論判したが、校長はついにうんとはいわなかった。そこで、せめて写真だけでも参加させてくれといったら、それ、しぶしぶ承知した。
いよいよ卒業式の日になった。仲のいい子が写真もって座って、さあこれから式がはじまる瞬間、九時ちょっと前の、一瞬しーんとした時間、そのときに、パタン、って講堂の腰板が、写真もった子のすぐそばの腰板が外れて、すうって風が入った。するとちょうどそのそばに来賓の、お寺の和尚さんが腰掛けていたが、
「お、誰にも呼ぼらんねえから一人ではいってきたか」
って声かけた。先生方も生徒も父兄も、みなぞっとしたという。
式が終わると担任の先生は写真を返しにその子の家へいった。するとその子の母ちゃんが実は、といったそうである。
仏壇の前に座って、ああ今から卒業式はじまるな、と思って、机の上に制服と帽子とかばんをきちんと並べ、線香立てて、時計をみたら九時ちょっと前だった。そのとき、ガラって玄関の戸があいたから出てみたら誰もいない。なのに、戸が五寸開いていた。おかしいなと出てあたりをみたが人影もない。
え、それならそのとき、家を出て、学校さきたんだ。九時ちょっと前のいよいよ式っていうとき、パタンって腰板外れてね。なら先生、家の子、卒業式へ出たんだな。そうさ出たんだよと、親と先生は、手を取りあって泣いたという。
死んだ人は七が宿から蔵王山に登って三途の川へいくという。うれしくていくときほっほっと笑いながらいくという。悲しくていくとき、しくしく泣く声するという。その子はどんな思いで山登ったんだべ、あのバカ校長。
19 夢の鉢/20 病気を持っていく/21 クリームパン/21 山での失くしもの/23 列車を止めた熊/24 六人の小坊主/25 死んだ自分を見る/26 蛍とりと火の玉/27 田芋畑で/28 死人道/29 指ノ浜(さすのはま)の漁夫たち/30 火にあたる死者/31 天雄寺の行列/32 園(その)どんの火の玉/33 産婆嫁ごもみた火の玉/34 火の玉の閲兵/35 火の玉の案内/36 火の玉に救われる/37 父ちゃんの内緒ごと/38 蛍もみ/39 天狗の花火/
40 天狗の神かくし
私はよく青梅と奥多摩の間をことことと単線で走っている青梅線に乗って御岳(みたけ)の宿へ仕事を持っていく。昨年その宿の女主人が郷土史家の清水利氏を招いてくれた。そのうちに思いもかけず、神かくしの話になったのである。
青梅線がまだ私鉄で青梅鉄道といっていた時分の……いや、年月もはっきりしていて、大正12年の7月、あの大震災のちょっと手前の夏の朝のことだったという。
土地の男衆が、日向和田駅の西の石神入の細い小川に沿って奥に入ったところで、朝草刈りをしていた。と、しくしく泣く声がする。振り返ってみると五、六歳の女の子が山道を泣きながらたどたどと降りてくるのだった。
見かけない子だが、お前はどこの子だ。男衆が声をかけたが、泣きじゃくりながらいう言葉がなんとしても聞きとれない・そこで女の子をおぶって日向和田の駅へ連れていった。
駅長はその子の耳慣れない言葉や着ているもの、藁草履などから、どうもこれは東北地方の山村の子に違いないと考えた。お手のものの鉄道電話で立川の駅長に事情を話し、新宿、上野、米沢、盛岡、仙台などへ調査を依頼した。子供は社宅へ連れ帰り奥さんに世話させた。
盛岡からの通報が入ったのはその日の夕方であったという。女の子は岩手県の山村の子で、前の日まで近所の子と鬼ごっこをして遊んでいたという。それが、ふっと姿を消した。それっきりどこを捜しても姿がない。村中が総出の騒ぎになって、かやせ、戻せと松明の火をかざし、鉦を打ち鳴らして捜したが、一夜明けても女の子の姿はなくて、神かくしかといいあっていたところだった。
やれやれよかった。それでは早速送り返してやらねばと、翌朝、大きな木の札に岩手県の、こうこう、こういう駅までこの子を送ってもらいたい。親はどこどこの村の者でこの子の名はこれこれと記し、女の子の首からさげ、握りめしをたくさん持たせて列車に乗せてやった。数日経てその子の両親から、たどたどしい礼状が日向和田の駅長あてに届いたそうである。
何としても不思議なのは、岩手の山の中にいた子が翌朝早く、青梅の山の中にぽつんとなぜ立っていたかということで、女の子の村では天狗さんにさらわれたといっていたそうである。
握りめしを握った駅長の妻女はついさきごろまで存命で、清水氏とも昵懇だったという。
41 天狗の酒買い/42 天狗のかかになった娘/43 いなくなった女の子/44 狐の提灯/45 狐の魔術師/46 五代目の子にたたった狐/47 大蛇に呑まれた子/48 大蛇を焼く/49 灰キノコ/50 カラスの八卦/51 夢 枕/52 死を告げにきた英霊/53 カヤのすみで/54 夢で帰る/55 私におくれ/56 夢の足袋/57 夢の風景/58 蛇皮線が鳴る/59 馬の夢知らせ/60 馬に生まれ変る/61 夢の幽霊/62 五人目の客
あとがき
ここに収められたのは、ことし1984年4月9日から50回にわたって「西日本新聞」に連載されたものである。草地勉氏より依頼があったとき困惑して、"私の遠野物語"といった感じでよければ、といった。快諾されて6月21日まで紙面を頂いたが、実はまだ一話も掲載されないうちから筑摩書房の橋本靖雄氏が、その話、戴きましょうといって下さった。有難いことであった。
ならば綿密なる構成の下に整然とした世界を展開すればよいのに、生来の怠けぐせがあって、その日その日を楽しむような、のどかなまとめ方となってしまった。終了後、新たに十余話を書き足したが、幾らでも書きたくて困った。それほど限りなく翻はあるのである。そのため、今回は、なるべく身近な人が話してくれたものを中心としてまとめた。
新聞に掲載中、また掲載後、多くの方より私にもこういうことがあった、とお便りを戴いた。どうかこの本を読まれた方々も、あったることをお寄せ頂ければ幸である。頂戴した話は、大きくいえば日本の財産として何らかの形で記し、留めておきたい。これは本当に大切なことだから、と私は思っている。
この中で一つ、靖国の軍帽の話が気懸りであった。歩いている道がふと見まわせば戦前のいつか来た道に似ている。その傾向を助ける結果になりはしないか。庶民の心のかなしさに、加えずにはいられなかったのだが。
忘れ難い人であった筑摩書房の中川美智子さんにこの仕事を担当して頂いたことは仕合せであった。また応接間に掛っていた一枚の絵を装傾にと目に留めて頂いたことも幸であった。松谷春男は兄である。
最後に多くの話をしてくださった方々へ感謝をこめて筆を擱く。
1984年10月19日 松谷みよ子
解説 "いま、を語り継ぐ"ということ 吉沢和夫
松谷さんが現代民話の蒐集と整理を始めてからもう10年になる。そのきっかけになったのは木下順二氏が「文学」(岩波書店)1952年5月号に載せた「民話管見」というエッセーの中の次の文章であったという。
「まだはっきりと形は成さないながら、『現代の民話』の種が僕たちの社会の中に生れて来つつあることは疑いがない。その種は、突飛なようだがあるいは『税金』であるかも知れない。『再軍備問題』であるかも知れない。『菅証人事件』であるかも知れない。僕は僕なりに戯曲を書く人間としての立場から、これらテーマの素材とも言うべきもの-それらは確かに複雑であり巨大であり強烈である-を、現代という決定的な瞬間において生々しく定着させたいと思う。それは僕たちが僕たちの祖先の遺産を継承し、そこから新たな伝説をつくり出して行くためにどうしても必要なことなのだ。」
松谷さんはこの文章に出会って「目から鱗が落ちるような思いを致しました。もしそのひとことがなかったら、もしかして私は民話に出会うことがなかったのではないか、そう思われるほど大きな意味をもった言葉でした。」(「民話の手帖」第30〇号国土社)といわれるほどに大きな刺激と影響とを受けたという。ということは松谷さんと民話との出会いにとって「現代民話」という契機のもつ意味と役割は限り無く大きく且つ根本的であったということであろう。
では、松谷さんにとって「現代民話」とは一体何なのか、それは1950年代前半における木下さんの問題提起や当時の「民話の会」のこの問題に対する考え方と全く同一のものと考えて果していいのか。勿論基本的な考え方としてつながっていることはいうまでもない。だが、重なる部分とはみ出す部分、というより突き抜けている部分といった方がいいかも知れないような広い分野の伝承を包含していると私には思われる。
もう少し具体的にいうと、たとえぽ木下さんのいわれる「税金」「再軍備問題」「菅証人事件」といったようなまさに現代日本がかかえている歴史的・社会的な問題や事件を背景として生み出され語り継がれていくような現代民話、歴史家の色川大吉氏のいい方を借りれば「戦争と近代化」をライトモティーフとするような現代民話というものが確かにあって、松谷さんも「偽汽車」「密造酒」「軍隊」「銃後」等々といった現代民話を全国的に蒐集している。そしてこれらの民話は現代民話の中の重要な核をなしていることはいうまでもなかろう。
だが同じ「軍隊」の民話の中にも、本書の「52 死を告げにきた英霊」のような「死の知らせ」に属する話がある。また「銃後」に関する民話の中にも本書の「31 天雄寺の行列」のような「死の予兆」といった話も語られている。こうした「死の知らせ」や「死の予兆」といった話は、必らずしも「戦争と近代化」といった歴史的・社会的情況と結びついた語りとして生れてくるとは限らない。否むしろ日々繰り返される庶民の日常の暮らしの中にしっかりと根を張ってそうした語りは育くまれてくる。いわば人間存在の根源に根ざす民衆の心の世界と向い合ったところで生れ語り継がれてきたといってもいいだろう。死と向い合うことで生の意味を考え、生の価値を探ってきた人間たちの、これは人間存在の根源に根ざした語りの世界であるといい換えてもいいかもしれない。
この本の第一話から第二〇話まで立て続けに「死」の話が出てくる。「あの世」にかかわる「この世」での話である。
枕元に立って「おれはいま死んだ」という死者からの知らせを受けると、直ぐさま電気釜のスイッチを入れて飯を炊き、釜ごと風呂敷に包んで持っていって、駆けつけてきた人々に朝食をふるまう、きびきびとした主婦の話(第一話)。
母親の枕元に、ヘチマの模様の浴衣を着て紫の伊達締を巻いた女性が座って、母親の顔をじっとのぞきこんでいた。やがて電報が届いてその女性が危篤だという。急いで馳けつけた時、その女性はヘチマ模様の浴衣を着て紫の伊達締をしめ、眠るように死んでいたという話(第三話)。
いちど死んで生き返った農家の主人が、三途の川のほとりで若い嫁御から「死帷子を着せてもらえなかったためにいく処へもいけない」という訴えを聞かされてこの世に戻ってきたという。嫁御から教えられた村へいってみたら全くその通りで、そこの家では真夜中になるとチーン・チーンと仏壇のカネが鳴ったという。嫁御のあの世からの訴えをきかされて帷子を縫ってお寺にあげたら真夜中のカネの音はふっつりやんだという話(第一五話)。
挙げはじめたらきりがない。本文をよんで頂けばいいのであるが、これは噺家が高座で演ずる怪談噺や、オカルト趣向の怪奇話とはまるで性質の異なるまさに「現代の民話」である。炊きたての飯を釜ごと風呂敷に包んで馳けつける話や、死帷子も着せてもらえなかった若い嫁御の話など、庶民の生活の臭いがぷんぷん漂っているではないか。
「同じ人の27日の逮夜に、知音の者集まりて、夜更くるまで念仏を唱え立ち帰らんとする時、門口の石に腰掛けてあちらを向ける老女あり。そのうしろ付正しく亡くなりし人の通りなりき。これは数多の人見たる故に誰も疑わず。いかなる執着のありしにや、ついに知る人はなかりしなり。」
これは柳田国男の『遠野物語』の第23話に記されている話で、「同じ人」というのは第22話に出てくる佐々木喜善の曽祖母を指している。第22話というのは三島由紀夫が絶賛したという有名な話で、曽祖母の亡霊が衣物の裾で丸い炭取りをくるくるまわしたという例の話なのだが、柳田はこれらの話を「現在の事実なり」として記している。松谷さんがこの本の話を「あったること」として記しているのと、これは通底した話の捉え方といえるだろう。
明治末年近代化から取り残されたような東北の山間のひとつの村に語り伝えられた伝承を鋼のような鋭い文章で彫りつけた『遠野物語』について、民俗学者の谷川健一氏は、「柳田は一個の遠野を語ることによって、多くの遠野をと、呼びかけているのである。このあくなき普遍精神が『遠野物語』という固有の物語を不朽にした。遠野は固有名詞であると同時に、普通名詞となった。」(『遠野物語』解説、大和書房)といっている。柳田によって彫りつけられた人魂や幽霊や神隠しや天狗や河童やその他諸々の物語りは、日本中の町や村にも伝えられていた。伝承そのものに通底する普遍的な内容は、普通名詞としての「遠野」を各地に発見させた。
「人間がそこにあるかぎり、ふつふつと民話は生まれる」という松谷さんの確信に支えられてここに収められた62篇の話は、まさに現代に生きる日本人の物語であり、同時に人間の物語である。
大陸の戦場で幻のローソクの火に導かれて助かった話(第三六話)、敗戦で日本へ引き揚げる際に火の玉に導かれた話(第三六話)、「死を告げにきた英霊」の話(第五二話)、戦死者が夢の中で妻の許に帰ってきた話(第五四話)、故郷を眼の前にして船が転覆して死んでしまった復員兵や同じ船に乗りあわせて死んでいった食糧買出しの人びとの魂が予兆として毎晩火の玉の行列をお寺へ向けて並ばせたという何とも不思議で哀れな話(第一三話)、海で溺れ死んだ子の魂が卒業式に出席した話(第一八話)等々いずれも現代に生きる庶民の哀しみや苦しみが滲み出ているような話が、「あの世からのことつて」という視座から語られている。これはまさに『遠野物語』と共通するテーマやモティーフを「現代の民話」という視点に立って捉え展開したものといって間違いではあるまい。『私の「遠野物語」』というサブタイトルの附される所以である。最後に『現代民話考』出版記念会の席上、松谷さんが述べられた言葉の一節を記してこの拙い解説の締め括りにしたい。
「私どもの祖先はさまざまの出来事、戦世(いくさよ)のむかしをふくめて民話を語り伝えてくれたのです。それをいま、私たちのひとりひとりが聞き手となり語り手となって、私たちが生きているいまを語り継がなくて、なんとしましょう。……」(「民話の手帖」第三〇号)