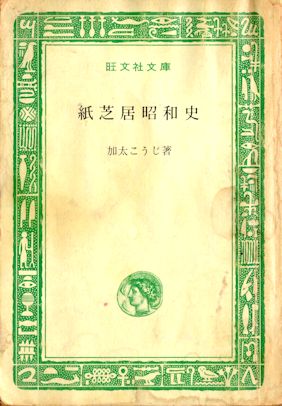
紙芝居昭和史 加太こうじ 著 旺文社文庫 旺文社
1979年9月25日初版印刷 1979年10月1日初版発行 0193-612-73-0724
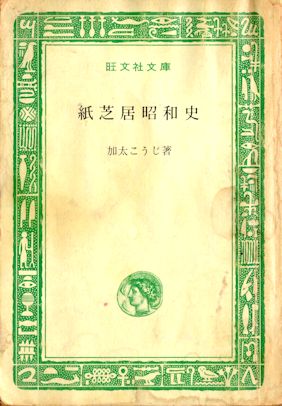
旺文社文庫は今は無いようです。代わりに、岩波現代文庫で2004年8月に、水木しげるさんの解説付きで発行されているようです。「原著にはない、『黄金バット』第16巻「怪タンク出現」の18枚もストーリー付で入っています。」と・・・。
ISBN4-00-603096-7
C0136
まえがき
紙芝居との出合い-小野照崎神社/『西遊記・孫悟空』/東京写絵業組合
世界経済恐慌/黄金バット-『黒バット』/テキヤシステム/話の日本社
レコードとラジオ-満州事変/『祖国を護れ』/昭和7年-荒川区三河島/紙芝居製作所/鈴木一郎
庶民芸術と怨念-『黄金.ハヅト』/プロレタリア美術運動/教師・翠川淳/山川惣治/『ハカバキタロー』/エロ・グロ物
紙芝居の確立-『天誅蜘蛛』/タクヅケ/太平洋美術学校/大日本画劇株式会社-昭和十年頃/会社設立
紙芝居の青春-『雨のブルース』/ミルクホール/軍国紙芝居と赤マント-印刷紙芝居/紙芝居コンクール/三河島報告詩
画劇会社争議/画劇会社炎上-大政翼賛会/南満州鉄道/東京大空襲/正ちゃん会
焼跡の雑草-ともだち会/焼跡ヤミ市/新日本画劇社/GHQと紙芝居-作家画家組合/『人民の旗』
第二建設期-冒険活劇文庫/伊藤和子/関東と関西/税金騒動
相馬泰三と子どもを守る会-相馬泰三/作品コンクール
画家群往来-凡天太郎/水木しげる/白土三平/小島剛夕/紙芝居の死
あとがき
紙芝居の作り方・演じ方
解説 鶴見俊輔
まえがきより
劇画、ストーリーマンガと深いかかわりがある紙芝居。あるいは幼い日の思い出と切っても切りはなせない紙芝居。また、ある年代の人にとっては戦争の記憶とともにあった紙芝居。その紙芝居が、日本のほとんどの町から姿を消して久しい。もちろん、ほんのわずかは今でも各地に残っているが、その姿を見かけると、私ですら意外なものを見たという感に打たれる。
私は昭和7年の春から紙芝居の台本を作り絵を描いて28年問を紙芝居作りですごした。青春時代と壮年期の大部分を紙芝居でくらしたのである。私は紙芝居潰滅後、物書き業になったが、そのとき、私以外に紙芝居の歴史をまとめる者はいないと思った。それは私の一生の記念碑であるとともに、日本の一時代を記念し得る庶民文化の歴史でもある。
そういう観点から、昭和の戦争の歴史とともに起こり、戦後の近代化によって歴史のなかに埋没し去った紙芝居史をまとめることにした。さいわいに、紙芝居の歴史を作った多くの人が現存しているので、それらの人の協力も得られた。
何かにつけて紙芝居的といわれた浅薄なる存在、それがのちに白土三平の『忍者武芸帳』や水木しげるの鬼太郎物その他を生むのである。一般の文化的と自負する人々から見れば浅薄と見える紙芝居に、青春の情熱を賭けて生きたのは私だけではなく、多くの紙芝居作家画家すべての態度だった。そのことを軸として紙芝居の世界に展開する人間ドラマをえがき得るならば、私は大いに満足である。そう思って筆をとる。ご熟読、ご批判をいただきたい。
この本を、紙芝居によって生きた青春時代のすべての仲間にささげる。
紙芝居画家として名もなく死んでいった何人かの仲間にささげる。
街々を拍子木を打ち鳴らし、太鼓をたたいて飴菓子を売り、紙芝居屋として子どもたちとともに一時期をくらした人たちにもささげる。
また、紙芝居を好んだすべての人たちにささげる。
すぎ去り、ほろびたものはなつかしいが、その過去の実体のなかから、これから生きることへの何ほどかの示唆を得ていただけるなら、この本を書く私としては望外のよろこびである。 加太こうじ
あとがきより
この紙芝居の歴史を書き終えて私は自分の一生にひとつの区切りがついたように思った。同時代に、同じ釜の飯を食って生きた仲間の記録は、紙芝居潰滅後、文筆業に転じた私が書かなければ、ほかに書く者はないと思いこんで十数年をすごした。今、立風書房と、その代表者である下野博、編集者稲見茂久その他の人の好意と協力によって、ようやく、そのあらましを書きあげることができたのである。はじめに、それらの人々のご苦労に、厚くお礼を申しあげる次第である。1971年夏 加太こうじ
文庫本へのあとがきより
昭和初期の不況を背景としてはじまった紙芝居業は、戦争の時代と、敗戦後の混乱期を経て、日本が石油産業を中心とする戦後の再近代化の時期に衰退しだして、平和と繁栄、経済の高度成長がいわれだした昭和33年には消滅の道をたどりだした。そして、この文庫本への序文を書いている昭和54年現在では、東京に五、六人、全国で三十人ほどの紙芝居屋がいると、推定されるような状態になってしまった。昭和28年の全盛時には東京三千人、全国五万人を算する紙芝居屋がいたことを思うと、今昔の感ひとしおである。
紙芝居は失業者の飴売り行商からはじまったといってよい。歌舞伎は念仏踊りと売春からはじまったともいえるし、落語は生活の資としての投げ銭を乞うために、街路などで小噺をきかせたところからはじまっている。古くをたどれば、ヨーロッパにおける文学と歌の発生と普及を、放浪のうたい手に見ることができる。それとよく似たものに室町時代における盲目の放浪の僧などによる浄瑠璃の発生があるし、さらにその前身としての平曲もある。
芸能、芸術といわれるもののすべては、屋根のないところ、いいかえれば大道や広場から発生したのである。歌舞伎は河原から、講談、落語、浪花節は街路から、映画ですら初期は太陽の光をもって撮影したのであって、当時、舞台・板の上で芝居をしていた俳優は、映画俳優を土の上で芝居をする者としていやしめたのだった。
紙芝居屋は大量の失業者が資本主義社会の発展の産物として発生したとき、日本の大都市のうちの貧民街、裏街、場末といわれるところから、組織を持たない失業者、すなわちルンペンプロレタリアートが、糊口の資を得るために、一時しのぎにやりだしたことから定着したのである。
この『紙芝居昭和史』は、私の体験を通して紙芝居の変遷を叙し、併せて昭和史を簡略ながらも知って頂く本として書いた。はじめは昭和46年に稲見茂久氏という立風書房勤務の若い編集者のすすめによって、立風書房からの出版を目途として書きおろしたものである。東宝映画はそれを原作として『黄金バットがやって来る』という劇映画を作った。
-絶版となっていた『紙芝居昭和史』を、旺文社の厚意によって、その文庫中の一冊にくわえて頂いたということは、私のみならず、紙芝居の世界で生活してきた者にとって、新しい記念碑を建ててもらったようなことになる。-
くどくもくり返すが、紙芝居は紙芝居屋の発生と共に発展して定着したが、今は大道芸の一つというよりは、幼稚園、保育園、小学校、あるいは児童のための図書館等が利用することが多い。河原で演じられていた歌舞伎が国立の大劇場で演じられるほどの変化ではないが、とにかく、屋根のないところではじまった紙芝居は、今は屋根の下で利用されているのである。そして、利用する人たちの都合で、紙芝居の初心といえるものが、ややわすれられかけてきた。そこで、この文庫本上梓に当っては、紙芝居の作り方を、新しく書きおろして付けくわえた。書いたのは私だが、こういうかたちでの作り方を、私が考えるまでには、この『紙芝居昭和史』に登場する多くの作家画家の意見が、紙芝居の歴史の全期間を通じて私によせられているのである。
終りに解説をお書きくだされた鶴見俊輔氏に謝意を表する。また、お世話になった旺文社の諸氏に厚くお礼を申しあげる次第である。
秋風東京に吹く日に加太こうじ
解説 鶴見俊輔
紙芝居の世界は人間らしい世界だったと、この本の著者加太こうじは回想して述べている。
それは、小学生のころから紙芝居の世界に入って、三十年その道にうちこんだこの人だけの感慨ではないと思う。道ばたで紙芝居を見たことのある何百万人もの旧世代の人びとが、共感をもつことのできる意見ではないか。
昭和のはじめには、都会にたくさんのあき地があった。そのあき地や、路地の入口にこどもをあつめて、紙芝居のおじさんが語りはじめる時、こどもたちの眼は箱の中の絵にそそがれる。その集中した表情、笑いと怒りにこたえて、おじさんは、話しをすすめる。
あめを買ったものだけが見られるという規則があるにはあったが、それはかならずしもまもられていなかった。うしろのほうから、あめを買わずに見ていても、おいはらわれることはなかった。今の映画劇場だったなら、切符を買わないで立見するなど許されるはずはない。
おじさんとこどもたちのあいだのこのような親密な交流を、紙芝居の去った今日の日本で、私達ちは、どれほどもっていると言えるだろうか。
なるほど、加太こうじの言うように、紙芝居は、機械化された今日の日本の大衆芸術の中にも、さまざまの痕跡をとどめてはいる。漫画雑誌や、テレビ劇画の中に、私たちは、紙芝居の中ではじめてあらわれた創意が生きつづけているのを見る。しかし、週刊漫画雑誌とテレビとには、かつての路地やあき地にあった親密な交流を求めることはできない。
紙芝居が去ったあとにできた空白は、まだうずめられてはいない。現代の文明の中で、之の空白をどのようにうずめることができるか。かつて紙芝居とともにあった親密な交流を、どのようにとりもどすことができるか。
その問題は、現代を生きる私たちに課せられている。それは、紙芝居そのものを、昔どおりの形で復活させることができるかどうかという問題をこえて、この『紙芝居昭和史』が私たちに問いかける問題である。
-そのような経歴をもつ人の著作として、この紙芝居史は、史実をひろく見わたして記したというだけではなく、隅々にまで血のかよった回想記となっている。
加太こうじにとって、紙芝居は、友人との出会いの場であり、その筆によって、紙芝居史上のさまざまの人物に、私たちは会うことができる。
紙芝居というものの性格がのりうつってしまうためか、紙芝居をなかだちとして知りあった人びとは、そのつながりが機械的なつながりになりにくいようである。
昭和34年以後、文筆家となった加太こうじが、紙芝居の歴史にたちもどって、その仕事をともにした人々の肖像を克明にこの本にうつしたのは、紙芝居をとおして知りあった人びとが、どれほどあざやかに今も彼の中に生きているかを示している。
この本にあるように、私がはじめて加太こうじに会ったのは、昭和34年2月のことである。
この本の中に出てくる永松武雄、松井光義、凡天太郎、山川惣治などの諸氏にも、加太さんをなかだちとして会ったことがある。
その時からすでに20年たった。加太さんは、私が学校では教えられなかったことを、実に多く教えてくれた。加太さんと加太さんの紙芝居学は、私にとって、大学をこえた、もうひとつの大学だった。