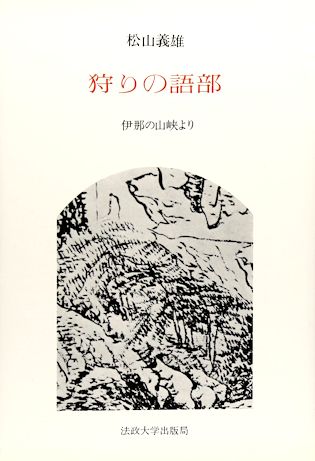
狩りの語部-伊那の山峡より 松山義雄 著 法政大学出版局 写真=周はじめ
1977年2月20日初版第1刷発行 1977年5月20日第2刷発行 1039-20070-7710
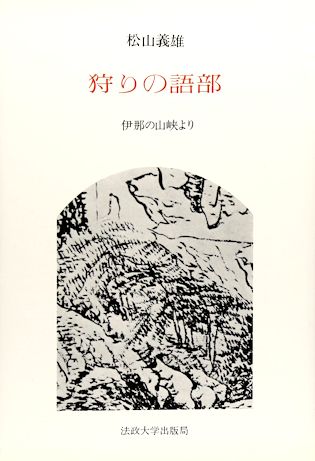
狩リの語部 目次
熊のしりもち
1、秋山の饗宴/2、穴こもりの仕度/3、穴熊・寒熊/4、熊の穴/5、穴を出る熊/6、夏から秋へ/7、秋の木の実と熊祭り/8、熊のあたり/9、熊猟とおし/10、肉食と熊オシ/11、山の木の実と熊/12、青野のころ/13、熊山騒げ/14、親熊・子熊とたつま猟/15、熊の胆/16、熊のこうがい
猪(しし)の十六
1、猪鉄砲・猪土堤/2、猪わち/3、うりん坊とかたぐろ/4、シシぼい/5、健啖家の猪/6、食べ物の好き嫌い/7、猪のぬた/8、茅刈る猪/9、アマスとねす/10、シシの十六/11、月の出と猪/12、犬がけとたつま/13、ウツ鉄砲/14、においゾメ/15、しし買いと猪のい
日本狼の墓標
1、送り犬/2、送り犬対策/3、狼の遠吠え/4、狼と馬/5、犬落し/6、狼の毛皮/7、へいぼう/8、狼の牙と骨/9、狼害と病狼/10、焼畑と狼害/12、犬を襲う狼/12、死者をあさる/13、危害を加えない狼/14、犬狩り/15、犬狼交配種/16、お七夜祝い/17、狼神社
伊那の狩り犬
1、えんのこ/2、いちもつ、にもつ/3、狩犬のめきき/4、犬の訓練と環境/5、犬のたて/6、カメと混血
あとがき
私はこれまでに自著の『山村動物誌』(昭18年)、『山の動物記』(昭25年)、『猿・鹿・熊』(昭26年)、『山国の動物たち』(昭28年)、『山国の神と人』(昭36年)などに、伊那谷の野生動物について書いてきましたが、こんどそれらを動物別に整理したうえ、さらに未発表の資料をたくさん加え、ここに新たな意志をもった一本を創り出すことができました。本書「狩りの語部」がこれです。
この書物に散見される猟人の名前はいずれも実名でして、昭和初頭以降の一時期、それぞれの峡谷において勇名をはせた猟人ばかりで、そのいずれもが根っからの庶民であります。ところでこの書物で猟人、あるいは猟師と呼んでいるのは、すくなくとも狩猟に関する、伝統的な教養や知識を身につけた人々のことでして、近頃輩出するスポーツとしての猟を楽しむハンターのことではありません。
私がこれらの猟人に親しみを覚え、接触を求めるようになった動機は、近代の機械文明や文化に粉飾されることのない日本人の姿を、猟人の生きざまの中に求めたためであり、もう一つはそうした生活を維持してきた山村の風土に、限りない思慕の情を覚えたからでした。とは言え、これは多分に心象的なものでしたが、とにかくそうしたものに引かれて、私の三峰川谷通いが始まったのですが、そこで私が知ったのは、猟師の語る話の節々にかくされている「狩りの語部」としての性格でした。そこで私は、ひょっとしたらこの話の中には、日本の古代に通じるようなロマンの破片が埋もれているかも知れないと思うようになり、そんな資料を求めて私は三峰川谷からさらに小渋谷へ、さらに遠く遠山谷へと、語部としての猟師を訪ね、その話に耳を傾けたものでした。
私の会った猟人は幸いなことに、誰も彼も話好きの人ばかりでしたが、彼らは「語部」の常として、わが話をわが手で記録するような煩わしい仕事には、一向に興味をもたない人たちでしたから、話の輪の中で私はいつも祐筆的存在として、またそれに心から満足して、忠実に鉛筆を走らせてきました。
こうして、私の書き散らした動物に関する文章が幾冊かの本になり、こんどまたこのような纏まった形の本になるまでには最初の採集から数えて40年の歳月が経過しています。その間に、あの時既に年老いていた「語部」たちは世を去り、今となってはこれらの人に、自身の語った記録を手にとって確かめて貰えないのが残念に思われます。
ところで猟人の語りのなかには伝承的のもののほかに、科学的のものもふんだんにあります。なかでも名猟人として世に喧伝されるほどの人ですと、野生動物の生態・習性について抜群の知識をもっているものです。日本に動物学が渡来する以前、または動物生態学の起る以前、野生動物の生態に精通する"博物学者"といえば、山の猟人をおいて他になかったのではないかと思われるほどですが、では優れた猟人がなぜに生態・習性に関して、それほど豊富な知識をもたねばならなかったかと言うと、狩猟というものは、動物の生態・習性に関する知識を土台にして、その上に組み立てられるべき行為であり、それが欠けている場合、猟のコンスタントな成功はおぼつかないものだったからです。したがって猟人が優秀であればあるほど、いきおい生態・習性に関する話が多くなるわけで、本書にもそんな理由から、生態的な文章がたくさん記されています。しかし本書は、動物の生態を主題に据えた本ではありません。
意図するところは、動物と人間とはこれまでどんな対立関係・依存関係にあったかを探り、これに照明をあてるとともに、環境破壊や環境汚染が乱舞する現在の日本において、人間と動物が共存できる限界を問われる日があるなら、その時本書は山の語部たちの証言として世にとりあげられる、そういう本でありたいと念じています。
さて本書のために、『カラスの四季』その他の名著で知られる周はじめさんが、詩情溢れる写真を沢山お寄せ下さいましたが、これらの写真を撮るため昭和50年9月には周さんと編集長の稲義人氏が、また51年1月には周さん単身の来伊がありました。私はお二人を案内して私のフィールドをかけめぐりましたが、この2回にわたる撮影行の6日間、山また山の峡谷の嶮路を終始車を運転してくれた飯田長姫高校勤務時代の同僚で、現在茅野高校在職中の宮崎俊雄教諭、また編集担当者の松永辰郎さんなど、本書の上梓にあたりご尽力いただいた以上の四氏に、厚くお礼を申しあげます。
(1977、1、7、上郷町下黒田の小さな白き家にて伊那山脈を望みながら、著者)