日本中世の民衆像-平民と職人 網野善彦 著 岩波新書 岩波書店
1980年10月20日第1刷
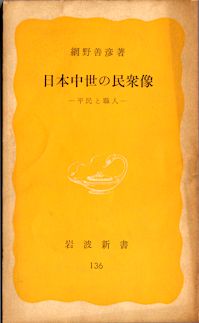
目 次
はじめに
二つの常識/言葉の変化/自然/自由/地/ゲザイ/散所/清目/日本史のなかでの中世/平民と職人/
まず最初に、中世社会自体について一般的に若干ふれておいた上で、主題に入りたいと思います。ここで中世と申しますのは、常識的に平安時代末から戦国時代までの時期を考えていますが、この社会は、ほぼ南北朝内乱を境として、大きく前後に分けることができると思われます。これからのべてみようと思っていますのは、主として南北朝より前の時期、中世前期の社会に関連する問題であります。
よく指摘されることですが、中世後期、すなわち室町・戦国時代の問題は、おおよそ江戸時代から明治以後のわれわれの常識で理解ができるといわれています。その時代の生活や文化、言葉などについて、われわれはとくに違和感を感じないでつかめるといわれているわけで、日本の伝統文化は、室町時代のころが一つの出発点と思われます。ところが、中世前期、鎌倉時代以前の問題になりますと、どちらかといえば古代につながっていく面がありまして、必ずしもわれわれの常識では理解しがたい異質なところがある。中世前期の社会がわかりにくく、ときに大きな誤解を生んだりする原因はそこにあるのではないかと思われるのであります。
なによりもまず、われわれがふつうの日常生活で使っている基本的な言葉の意味が、南北朝の前と後とでは、大きく変ってしまう場合があることを考えておく必要があります。そういう例はいくつかあげることができますが、たとえば、「自然」という語は、戦国時代には、「もしも、万一」の意味で使われることが多く、現在の感覚でこの言葉を解釈すると、史料の意味がわからなくなってしまいます。
第Ⅰ部 中世の平民像
1 平民身分の特徴
「平民」という言葉/百姓/身分を示す言葉/常民/権利と義務/自由民/封建的隷属民/封建地代/年貢と公事
2 さまざまな年貢
年貢の語義/首長制の問題/上分/米以外の年貢/年貢品目づくし/交通上の条件/「新猿楽記」の諸國土産/諸國土産年貢品目/中性的な年貢体系
3 年貢の性格
年貢の賦課徴収/鉄年貢/合子年貢/基準としての田地/交易の必然性/交換の場/貨幣流通との関係/平民的生産/鉄の生産
4 水田中心史観の克服
水田の位置/制度的性格/文書と実態との乖離/ハレとケ/文書の作成と伝来/研究の空白/年貢とは何か
5 公事の意味するもの
公事という言葉/雑公事/年中行事/農業労働/大田植/三日厨/供給/酒肴の席
6 「自由民」としての平民
共同体行事/名の均等化/「公」の意味/負担の意味/人身所有のあり方/土地所有のあり方
第Ⅱ部 中世の職人像
1 職人という言葉
「自由」の特権/手工業者/荘園の「職人」/職人歌合/道々の者/芸能/「職」と「芸能」
2 職人身分の特徴
年貢・公事の免除/特権と差別/権門への奉仕/交名帳/諸方兼対/下人・所従との違い/
3 遍歴する職人集団
自由往来/廻船鋳物師/東国の海の道/黒潮の道/遍歴する職人集団/職人の由緒書/東国と西国
4 櫛を売る傀儡
香取田所文書/御櫛生供御人の訴え/近木郷の櫛造/傀儡の集団/自立した芸能民集団/
5 職人としての唐人
唐人集団/「大唐」の「大工」/橘屋の唐人座/唐人の往来/開かれた社会/
おわりに
中世前期の社会/歴史の節目/感性的要素の役割/色と服/飛礫/音声の世界/民族史的転換/新しいつながり
冒頭にもふれましたが、平安末期から戦国時代にいたる中世社会は、荘園公領制を基礎構造とし、身分制や国家あるいは文書の体系等々を含めた諸制度のあり方をみても、たしかに一つのまとまった構成をもつ社会と考えられます。この社会をいかなる社会と規定するかについて、いままでいろいろな議論があり、一方にはそれを家父長制的奴隷制社会とする考え方があり、他方では農奴制にもとつく封建制社会であるとする見かたがあって、すでに長い論争史をもっています。しかし、現状をみますと、奴隷制、封建制という言葉、範躊そのものが流動化しつつある。封建制という言葉によって理解されている内容自体がずいぶん多様で動いております。
さらに、そうした社会構成を考え、議論するさいの前提となる基本的な概念、土地所有、地代などの概念自体が、もう一度徹底的に再検討されなくてはならない状況にあると私は考えております。その意味で、これまでの既成概念にとらわれずに中世社会の特質、その構成を、もう一度新しく浮かび上がらせるためには、解決しなくてはならない問題がまだたくさん残っております。
ただ、そのなかで、中世社会はその真中のころ、南北朝の内乱期に、一つの大きな節目をもっているという点について、言葉の意味の転換などを中心に、いろいろ説明してきましたが、これはたんに中世だけの問題でない大きな節目だと思われます。多少冗談のように聞こえるかもしれませんが、いまわれわれがちょうどその末期ぐらいに生きているのではないかと思われる高度経済成長期の社会、もちろんこれは近代社会のなかの一時期ですが、この時期におこった日本の社会構造の変化がきわめて深刻なものであることはいうまでもありません。日本の歴史全体のなかで、南北朝内乱期の大きな転換と比較するとすれば、まさしくこの時期が最も適当なのではないか。そのくらいの変化が、南北朝内乱期にあったのではないか、と私は考えております。いわばそれは民族の体質、あるいは民俗の根底に関わる大きな構造土の転換期だったのではないか、と思うのです。
この転換以前の社会は、古代や原始社会になお通ずるものをもっており、原始性、呪術性に富んだ社会でありまして、近世以降の常識でたやすく理解しがたい要素が、この社会にはまだかなり支配的な意味をもっているのではないか。さまざま「芸能」それ自体が、まだマジカルな意味をもってとらえられるような一面があったのでないか。またその反面、そこでは、さきに詳しく説明したように、異民族や非人、遊女などもまだ差別の世界に封じこめられてはいない。それぞれ自立した独自な集団として活動しうるような開かれた一面をもっている。この時期までの日本の社会はそれ以後と比べて、まだ一個の民族体として十分のまとまりをもっていない状況であったともいえるかと思います。
ここでは東北、東国、西国、九州のような地域が条件によっては、それ自体、独自な民族となり得る要素をそれぞれにもっていたともいえるように思われる。とくに東国と西国は、さきに強調しましたように、場合によっては別の「文化」をもつ「民族」で、別個の国家になる可能性は十分ありえたし、事実、東国国家の存在、天皇と異なる権威をもつ国家は実際に存在したと私は考えております。その意味でも日本列島に住む人々の社会は、この時期、まだ民族体として十分の成熟にいたっていない。そういう時期として南北朝内乱以前の日本をとらえることができるとすれば、この転換期は、社会構成の次元とは異なる次元の転換といっても差し支えないのではないでしょうか。
いま呪術的、原始的と申しましたが、おのずとこの時期の社会では、まだ感性が大きな意味をもっていたと思われます。目にみえる色、服装、あるいは鼻で知る匂い、香り、耳で聞く鐘などの音、あるいは手や足による触覚等々、そういう感性的な要素が文字による認識以上に、庶民の世界では、その判断に決定的な役割を果たしていたのではないか、ということであります。
あとがき
本書は、1979年10月2日、同月9日の岩波市民講座における講演記録を整理し、「日本中世の平民と職人」と題して、『思想』1980年4月号、5月号の誌上に、2回にわたって発表した論文に、「忘れられた歴史」(『世界』1978年12月号)、「『新猿楽記』の諸国土産について」(日本思想大系、月報62号)などの趣旨をもりこみ、さらにかなりの筆を加えて、再構成したものである。-
われわれをとりまく状況は、天皇をふたたび日本民族の統合の中心にすえるべく、急速に動きはじめている。それは、歴史を学び、その真実を究めようとする者に対し、これがもとより歴史の事実に即したものではないことを明らかにするとともに、民衆自身の生活そのものの多様な営みのなかから、民族がそれとして形成されてくる道筋を具体的に解明することを要求している、と私は考える。本書もまた、その課題を達成するための一つの試みにほかならない。もとより考え違いや誤りも多いと思うので、そうした点については忌揮のないご指摘をいただき、さらに考えを煮つめてゆきたいと思う。
私事にわたるが、本書の発刊されるころには、すでに私は長年勤務してきた名古屋大学文学部を離れて、新たな職場、神奈川大学短期大学部に移っていることになる。しかし本書は、あらゆる意味で、私の名大文学部在職申の産物であり、ここにのべたことのすべては、講義や演習のさいに発表し、また職場での日常のなかで開陳してきたものにほかならない。そうした私の拙い意見に、つねに熱心に耳を傾け、批判、教示、激励を惜しまれなかった、同学部の多くの学生、大学院生、研究生、卒業生、そして同僚の諸氏に対し、ここに衷心より、感謝の意を表したい。
また、『思想』誌上に発表してから日時のたっていないことを理由に渋る私を鞭撻され、ここまでことを運んでくださった編集部の伊藤修氏に、厚く御礼を申し上げる。
1980年9月1日 網野善彦