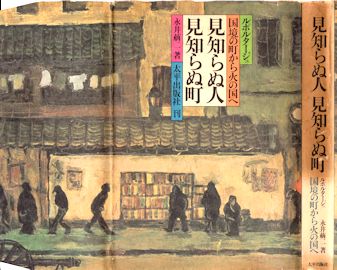
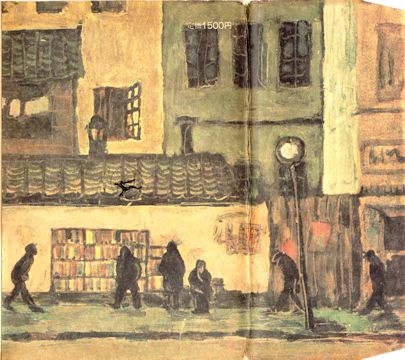
ルポルタージュ 見知らぬ人見知らぬ町-国境の町から火の国へ 永井萠二 太平出版社
装頓=粟津潔 編集=長津忠 1980年12月25日第1刷発行 0036-801208-4321
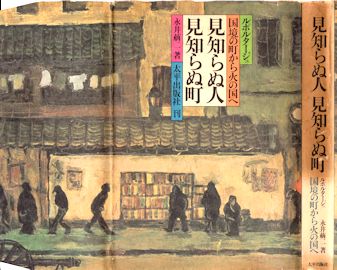
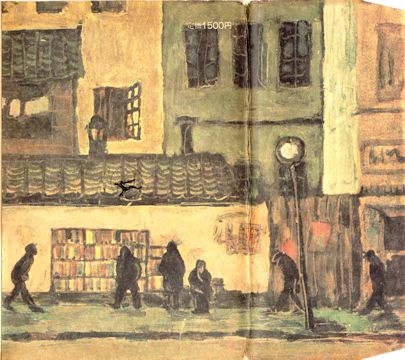

目次
Ⅰ はじめに
1 生をみつめる旅-まえがきにかえて
もうひとつの旅/越前和紙のふるさと/暗い思い出にもあたたかさ/松本清張氏と信州の旅/綾子さんのタベの祈り
Ⅱ
2 にっぽん各駅停車-鈍行列車で540駅の旅
最北端の町から/ウィスキーなめなめ世間話/鈍行客の話に耳かたむける/敗戦直後さながらの行商車両/連絡船上で/どの座席にもリンゴが/土地の人との心のふれあい/墨絵のような裏日本の風土/温泉がえりの婦人会/大阪発門司行鈍行列車/ビールがふさわしい山陽道/九州を南下/各駅停車の旅の終わり
3 冬から春への本州縦断-東経137度線を南へ
名も冷やかな氷見の町/暗く寝しずまった町/万葉集に歌われた海/万葉の遺跡も多い地方/氷見線から高山線へ/飛騨は寒暖の境/碧南のイメージと実景/産業都市の夢をおいかける/詩のあるフィナーレ
4 宍道湖-水郷の城下町を歩く
八雲立つ国/雨にぬれる松江大橋/古い湖の新鮮な魅力/すばらしい暮色の風情
5 津和野-4キロ四方の小城下町
方4キロの小城下町/歴史がつめこまれた町/津和野の人12傑/町をでて活躍した人びと/ひとり歩きがいい津和野/コイ群るる町の人びと
6 四国巡礼同行記-生と死を経めぐるお遍路さん
札所を歩く遍路のかげ/一夜の縁、それぞれの業/遍路同士の語りあい/すぎさった苦難の歳月
7 愛のノート『風』をまちわびる-青春の女流歌人たち
歌集『風』はいまどこに/すこやかに夫に添はん/六枚の名刺をたよりの旅/『風』の最初の提案者/青春をむなしくおくる/短歌が唯一
付記 世界一の超特急-新幹線「ひかり」が、はじめて東海道を走ったのが、1964年10月1日。「ああ、これでSL時代も、さらばか」と思ったのはまちがいだった。新幹線だ、ジェヅト機だとさわぐ声のかたすみに、あのもくもくとけむりをはき、山坂を一生けんめい走る蒸気機関車の退場をおしむ読者のなげきの声もきかれた。そこで、その年の12月、松本栄一カメラマンといっしょに、わたしは「日本縦断鈍行列車の旅」をくわだてた。
まず、国境の町稚内にとんだ。駅弁をほおばりながら、鉄橋をわたり、トンネルをくぐり、のんびりと旅をつづけ、翌年の新年号用の読物をつくった。
当時の駅前旅館は、朝夕食付1,900円。お酒特級三本、360円。つきだし100円とあり、高いところで、朝夕食付3,000円だった。
Ⅲ
8 民族音楽を愛する人たち-アルメニアの思い出
104歳のおばあさん/苦しい時代の思い出/思いがけない心のふれあい/だけど、心はやらないそ/別れのとき
9 あま色の髪の女-ブルガリア民話の旅
バルカン半島の秋/ぺートルのとんち話/金持の百姓と貧乏な百姓/いまの時代がいちばんいい/黒海の光をあびながら
10 トーポリの木の下で-ソヴェト民話の旅
中央アジアを西へとぶ/タタールのむかし話/アルマ・アタの町を歩く/心のなかのふるさと
11 70年のロシア-民族の心の旅
ナホトカからモスクワまで/民衆たちの顔と暮らし/ロシア人を裸にすると/ソヴェト国籍の日本人たち/かなしみこもる歌声/岡田嘉子の「女の一生」
付記 1970年9~10月にかけて、わたしは朝日新聞社から、ソヴェト、中央アジア、ブルガリアに特派された。『週刊朝日』のなかまたちは、「のんびりと旅をして、エッセイふうの読物でも連載したら……。ただ、亡命の女優岡田嘉子には、ぜひインタヴューすることだな」といった。
ソヴェト事情にくわしい朝日広告社専務の金田日出雄氏といっしょに、横浜からソヴェト客船に乗った。あの夏の日のたのしさが忘れられない。『モスクワの顔』などの著者であり、1965~68年、モスクワの。フログレス出版所に勤務したことのある芹川嘉久子さんから、予備知識を仕入れての旅であった。
わたしは、翌年、1971年8~9月にかけて、新聞4社・テレビ5社の18人の訪中報道団の団長として、文化大革命期の中国に特派された。当時は(いまもそうだが)、うっかりソヴェトの話をもちだしたらたいへん、中ソ対立の根ぶかさにおどろかされた。北京・上海・長沙・広州などを取材、「朝日新聞」の報道にあたるとともに、『週刊朝日』や『アサヒグラフ』に、「中国のバリ麻酔」「はだしの医者」「毛主席のふるさと」などを連載した。日中関係が正常化する一年まえだったから、マスコミは中国ブームで、テレビにかりだされたり、雑誌社からの原稿依頼で忙しい思いをした。
「四人組」が追放された現在、10年まえに書いた中国ルポを読みかえしてみると、まるでウソが書いてあるように思える。記者の書くものは、鮮度を失うとこんなにも色あせてくるのかと、実際報道の限界を思い知らされる。いや、時代の移りかた、変わりかたが、わたしたちの予想をこえてとぶように早いのかもしれない。わたしにとっては、思い出ぶかい中国ルポだが、この本からは除くことにした。
Ⅳ
12 傷つき荒れた「筑豊炭田」-豊州炭鉱事故から一か月
どろとボタでつまった坑道/廃屋から白いガス/会社側の無言の圧力/孤児たちのゆく道
13 さいはての「飢餓半島」-でかせぎの漁村をたずねて
さいはてムードだど…/ポシャッた夢の大企業/専業漁師は皆無にちかい/地元に企業さえあれば/生まれかわろうとする声
14 父ちゃんのいる正月-でかせぎから解放された一家の哀歓
じぶんの家がなにより/エノキダケの栽培に成功/楽しみは手紙を書くとき/いっしょならつらくない/希望に胸をふくらませ
15 生きのこった「青い目の人形」-アメリカ人形をまもったある反戦
生きのこった青い目の人形/傷痕をきざみつけた人形/人形をたすけた人
16 猪飼野の「しょっぱい歴史」-在日朝鮮人のさまざまな傷ぐち
「しょっぱい歴史」の町/永住権と民族の誇り/なんだ、朝鮮人か/子どもにだけはいい教育を/目を輝かせるわかものたち
付記 人と人との出会いという意味での旅と人生-といった感じのひとにぎりのルポをここに選んでみた。
わたしは、農村や漁村や炭鉱の町といった、日本の日かげの道を歩いて、さまざまな人生にふれるのが大すきである。はなやかな「繁栄」を誇る日本になっても、貧しい断層のなかに、かえって忘れられたたいせつなものが、いっぱいつまっているからである。知らない駅におりたとき、この町のだれかと知りあい、つぎつぎに取材の輪をひろげるのだと思うときの喜び。ききだしてきた、さまざまな身の上話を、宝石のように宿にもちかえる。そして、それらを一度、ばらばらにほぐして、そのなかから問題点をひきだし、もう一度、身の上話をくみたてなおしてルポをつづってきた。
V
17 反戦詩をつづって60年-樋口配天翁の悲願
つきそいのおじいさん/反戦叙事詩/苦しい生活にもたえて
18 「ぼくはこの診療所を離れない」-津軽の無医村にきた游紹陳先生
無医村の外国人医師/みるにみかねて/ぼくは、この村で死ぬ
19 ガー公先生と教え子たち-名物教師 小野美哉さん
天衣無縫の数学教師/六中の草創期から20年間/楽しみは教え子の来訪
20 かたすみからの発言-深尾実さんの下町情報
詩情あふれる文章/下町情報/小説家を夢みた日
21 日本の喜劇王が死んだ日-エノケンの泣き笑い人生
喜劇の王様/しわだらけの傷心の顔/さみしい楽天家
22 蝶々が語るわたしたちの「夫婦善哉」-南都雄二逝く
雄さんの死/女房やったら、看病できたのに/上方人情あふれる名司会
23 処女作を書いた思い出の土蔵-水上勉さんの涙
白幡の母さん/水上さん がんばれ/苦渋にみちた生活/内田家のやさしいひとびと
付記 わたしは、1946年から30年間ちかい朝日新聞社生活の大半を、『週刊朝日』編集部で鉛筆をにぎりつづけた。いまも社外寄稿家として、ときおり、原稿を書いている。入社したころは、用紙事情のきわめて悪いヤミ紙時代。競争誌といったら『サンデー毎日』だけだった。だから、まじめに生きる人間を描くだけで、おびただしい読者の手紙が殺到したものだ。-「ニュースより、その背後にある人間を描く」ことを、このころから信条にして、わたしは生きてきたように思う。
むかしは、マスコミが提供する情報量はきわめてすくなく、世間の要求のほうがはるかに強かった。だから、ナマのニュースをそのままなげだすだけでよかったのかもしれない。が、1955年、新聞社系週刊誌は大敵をむかえた。それは、『週刊新潮』をかわきりに、ぞくぞく発刊された出版社系週刊誌である。いつか40誌がしのぎをけずる時代がきて、もう、けなげに生きる人をおいかけるだけでは、読者は満足してくれなくなってしまった。
情報氾濫の時代になると、トップ記事やルポルタージュだけで勝負するわけにいかない。ナウな話題、ゴシップ……、小粒なタネを満載しなければならない。
いまのわかものからみれば、わたしの忘れがたい人は、古風な生きかたをしている、あるいはした人かもしれない。前二著『キムチの匂う街』『春風のなかの子ども』(ともに太平出版社刊)にもさまざまな人生を紹介したが、この本にも、いく人かそういった人を紹介したい。
Ⅵ
24 「韓国戒厳令」に直言する-金大中氏の悲痛な叫び
韓国の民主主義の死滅/権力欲から戒厳令を/受難がまちうけている
25 わたしは朴大統領退陣を直言する-金泳三氏インタヴュー
民主回復をまつ国民の期待/おいつめられた朴政権/帰国したらあぶない
付記 日本の政治家とのインタヴュー記事も無数に書いてきたが、読みかえしてみると、時間による蚕食をうけて、いちじるしく魅力のない記事になっている。ここでは、「剣がペンより強い国」韓国のふたりの悲劇の政治家との会見記を収録した(インタヴューには、「朝日新聞」元ソウル支局長の岡井輝雄記者が同席して質問にくわわってくれた)。それにしても、この二人のことばは、5年や10年の時間をとびこえて、なんと預言的な意味をもっていることだろう。
Ⅶ おわりに
26 わたしが歩いた時代-あとがきにかえて
童話の眼/かけだし記者の時代
この本も『キムチの匂う街』『春風のなかの子ども』とおなじように、おもに『週刊朝日』に書いたわたしの署名記事の一部をあつめてできた。人と人との心のふれあいを人生の旅というなら、本書はそのような意味での「旅」も念頭において編集されている。ひとりの取材者としてのわたしの報告のなかに、国籍を問わない民衆のよろこびやかなしみを読みとっていただければうれしい。
それぞれの章は、なんらかのかたちでつながりがあると思われるルポによって構成し、各章のはじめに、それらのルポをつづった当時のわたしの感想や時代背景などを「付記」として書きくわえた。
なお、Ⅳの「猪飼野の『しょっぱい歴史』-在日朝鮮人のさまざまな傷ぐち」は、『キムチの匂う街』Ⅲの「猪飼野・キムチの匂う街-『日本の中の朝鮮』に見る希望と哀しみ」と『春風のなかの子ども』Ⅳの「大邸のガム売り少年-『ユンボギの日記』」とあわせて読んでいただきたいと思う。
夢中になってすごした記者生活のあいだに、おそらく妻や子どもたちにはめいわくをかけたことが多かったと思う。わたしじしんが情熱的に動きまわる分だけ、家庭をかえりみることがすくなかったのはたしかだったろう。この本を、そうしてすごした家族たちに感謝をこめておくりたい。
1980年11月
紹介者注:「私が歩いた時代」のなかで、履歴に関する事項は、著者紹介ので紹介している。氏名一覧、永井萠二でたどっていただきたい。